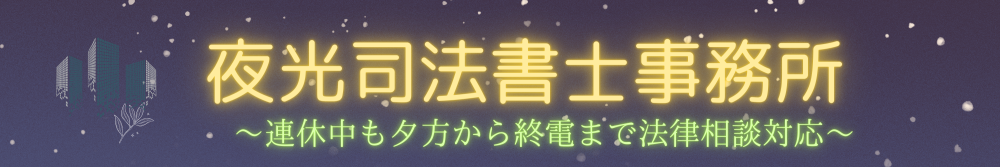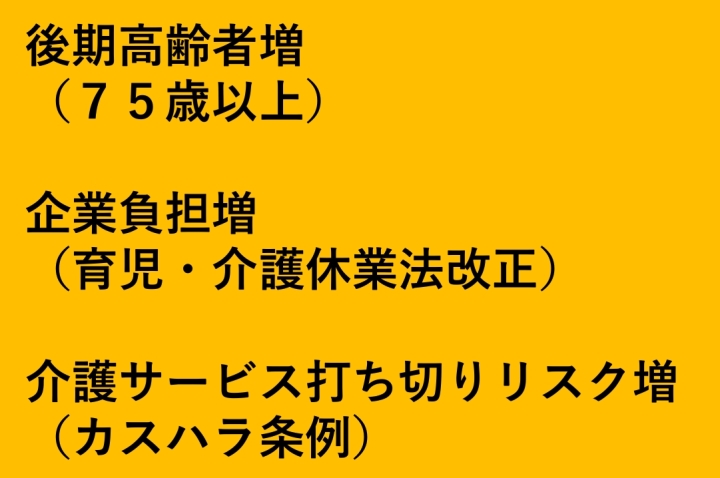従業員の方の介護離職対策をお手伝いします
従業員の方が介護離職を切り出した場合の対策・防止を当事務所は行っております。
方法としては、下記
「夜光司法書士事務所ではどんな対策が取れるか」をご覧ください。
しかしその前に以下①~⑥の記事を是非お読みください。
従業員の方が介護離職や長期の介護離脱を選択する背景や
会社でも対応が取りにくい等の各事情を纏めております。
介護離職は従業員、会社双方が被害者だと当事務所は考えております。
そのため仲間同士タッグを組んで対策を行うことが急務です。
本業務はそのような対策のお手伝いです。
 会社と従業員がタッグを組んで対策しましょう
会社と従業員がタッグを組んで対策しましょう
①育児・介護休業法改正について
2025年4月1日から育児・介護休業法の改正施行が始まりました。
改正には「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」が含まれています。
企業が従業員の親族の在宅介護に理解を示す内容の改正です。
以下概要になります(厚生労働省公開データより引用)
●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
上記のように仕事と介護の両立を目指した改正ですが
各企業は具体的に何をすべきかハッキリしていません。
そのためどのような対応をすれば良いかご不明な方が
未だ多くいるかと存じます。
対応例として、テレワーク設置、介護休業利用、
民間のコンサル事業者によっては
従業員の方に介護サービスを紹介する案内業務を取り扱っています。
確かに必要な対応ですが、これだけでは十分とは言えません。
在宅介護を行う場合、100%介護をサービス業者にお任せすることは難しいです。
親族の方の負担がどうしても多くなります。
そのため親族の方の介護負担を少なくする方法が別に必要となります。
 在宅介護負担
在宅介護負担
②今後のテレワーク業務について
育児・介護休業法改正の一つに、
「要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務」があります。
しかし現実の業務ではテレワークができる業種は少ないです。
対面必須の業務、生産、建築、その他社外秘取扱い業務担当者等
に該当する方はテレワーク対応は難しいと考えます。
加えて今後のテレワークについては世界的に縮小する可能性があります。
リモートワークが盛んなアメリカでは大企業がフルリモートから脱却しています。
例としてECサイト最大手某社に関しては2025年から週5出勤となりました。
ECサイト業務は大部分がWEB上で対応できるため本来はテレワークと親和性が高いと考えられますが、業務効率を重視して出勤に舵を切ったものと考えられます。
他にも世界的な大企業がフルリモートから段階的に出社に移り変わっています。
世界的にテレワークの効率を見直す時期が到来したことを意味しています。
ゆくゆくはテレワーク以外の両立支援策が必要になると当職は考えております。
 テレワークできる業種は限られます
テレワークできる業種は限られます
④仕事と介護の両立は可能か?
仕事と介護の両立は大変難しいとお考えください。
介護は本来、老人ホームや介護士といったプロの方にお金を払って
お願いすべきものだと当職は考えています。
しかし2025年問題で後期高齢者増加、介護士の人手不足も
原因となり親の介護を全て外部サービスに任せるということが
難しくなった背景があります。
運よく在宅介護の介護士が見つかっても家に来るのは週に2~3回、滞在時間は1~2時間という条件を提示されることもあります。
介護の大部分は親族が行う必要があることに変わりありません。
在宅介護のために、テレワークを導入しようにもそもそも
テレワークができる業種が限られています。
介護休業制度を利用しての介護も選択肢としてあります。
介護休業制度については以下をご覧ください。
【介護休業制度とは】
「労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業」です。
対象家族一人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
この休業期間中に
「市区町村やケアマネジャーへの相談、介護サービスの手配、
家族での介護分担決定、民間サービスを探す期間等」を
行うことを厚生労働省は推奨しています。
つまり長期戦の介護に備えるための準備期間です。
「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。
「要介護状態」を介護度で表すと要介護2以上に相当します。
要介護2とは2015年までの基準に照らせば特別養護老人ホームに入所できていた方です。(2015年以降は原則要介護3以上が必要)
つまり本来プロの手による介護が想定されていた方です。
このような方の在宅介護は訪問介護や介護休業を使ったとしても
難易度が高いものだと考えます。
また、厚生労働省は家族での介護分担の決定を介護休業中に
行うことを推奨していますが、
これが一番手間がかかると当職は考えます。
この負担をサポートすることが弊事務所の業務です。
詳細は「夜光司法書士事務所ではどんな対策がとれるか」
に記載しています。
 仕事しながらプロ並みの介護は困難です
仕事しながらプロ並みの介護は困難です
⑥「介護の押しつけ」の相談先は見つけにくい
本来親の介護は、外部のプロに頼り、足りない部分は扶養義務者が
協力して行うものだと当職は考えています。
仮に他の親族から介護を「押しつけ」られている場合
どこに相談すべきでしょうか?
・担当ケアマネジャー
➡ケアプランの作成等が業務のため親族問題には介入しません。
昨今ケアマネジャーを何でも屋として扱わないで欲しいという声明が関連団体より出されていますので、今後も業務外として応じないように考えられます。
・かかりつけ医
➡要介護者の医療行為が業務であり親族問題には介入しません。
・役所福祉課
➡相談をしても福祉課には他の親族を説得する等の権限が無い為期待する対策は取ってもらえません。
・カウンセラー
➡有料で話は聞いてくれますが根本的な解決策は出せません。
話を聞いて相手の心をスッキリさせるのが主な目的のためです。
いずれの団体に相談しても最後には
「ご家族とよく話し合ってください」と伝えられて終了です。
現在介護を押しつけられている、
将来介護を押しつけられそうだ、
等とお困りのビジネスケアラーの方は当事務所を相談先の候補に挙げて頂ければ幸いでございます。
代表の大内は 司法書士 兼 心理カウンセラーなので
心理面を考慮した法律対応でお手伝いできると考えています。
 効果的な窓口は中々見つかりません
効果的な窓口は中々見つかりません
夜光司法書士事務所ではどんな対策が取れるか?
働いている方が勤務先に対し、「介護離職」や「長期の介護離脱」を切り出すのはハッキリ申し上げると
異常事態です。
そもそも親の介護の場合、介護サービスと連携しつつ扶養義務者(親族間)が
協力して行うものです。
義務の内容は、金銭による支援が基本ですが、当事者が納得すれば直接的な介護支援という方法もあります。
本当にその従業員の方が仕事を犠牲にしてまでやるべきなのでしょうか?
ご本人の生活収入に直結する一大事です。
親族で協力して介護するにしては、いささか過剰な決断にも思えます。
つまり
親族からの介護押しつけの可能性がありますこの問題は中々表には出てきませんし、おそらく従業員も
「親族から介護押しつけられているから私がやるしかない」とは
会社に直接言いたくないと当職は考えます。
そのくらいデリケートな問題です。
仮に「介護離職」「長期の介護離脱」の原因が親族間の介護押しつけの場合、
当事務所で提供できるサービスがあります。
扶養義務を負っている親族を介護に関与させる手続きです。
親族間の介護協力を念頭においた対策を揃えております。
具体事例は「介護押しつけ対策」ページをご覧ください。
※当事務所では老人ホーム入居のご相談や介護サービスについての問い合わせ対応は行っておりません。地域包括支援センターや役所の福祉課等にお問い合わせください。人事ご担当者様におかれましては、以下の様な従業員からのお悩みを受ける機会も今後増えると考えます。
介護の押しつけが疑われる場合、従業員の方の意向を確認後に
弊事務所までご連絡頂ければ従業員の方と面談実施し、協力して今後の対策を考えていきます。
他の親族と介護協力が得られれば、「介護離職」「長期の介護離脱」を選択しなくて済む可能性もあります。仕事と介護の両立の可能性を意味します。当事務所が目指すものはこの流れです。
サービス・報酬について【法人様お支払い額】
当事務所では従業員の方の介護押し付け対策を行います。
以下は法人様にお支払い頂く額です。
現在は出張セミナーと個人面談サービスを提供しております。
面談後、従業員の方が当事務所とサービスを希望する場合は以降
従業員の方との契約になります。
本契約後の報酬は従業員の方から頂く形になります。
・法人出張セミナー(60分~80分程度)
従業員の方々に対し、介護押し付け対策セミナーを行います。
場所は出張先の会議室等をお借りします。
その他プロジェクター、スクリーン等もお借りします。
設備が無い場合はこちらで紙資料をご準備致します。
報酬:44,000円/1回
この他に仙台駅からの交通費が発生します。
片道2時間以上かかる場合は日当として11,000円追加で頂きます。
・従業員の方との出張面談(60分)
代表の大内が従業員の方と直接面談を行います。
「介護離職」「長期の介護離脱」に関する面談は迅速に行う必要があります。
あまりにも面談まで時間がかかると従業員の方が介護の面で焦ってしまい突発的に離職等を選択してしまう恐れがあります。
スピード勝負ですので要望があった日より1週間以内に
面談行えるように調整致します。
場所は出張先の会議室等をお借りしたいと考えておりますが、
面談日が土日等定休日になる場合は貸会議室料金も発生します。
※依頼者の第一希望日時等のご要望は最大限考慮しますが
ご期待に沿えない場合もございます。
※従業員の方が問題解決に前向きでは無い場合は面談はお受けできません。
本人の意思確認をお願いします。
※面談内容については守秘義務により従業員の方の同意が得られない限り法人様にお話しはできませんのでご注意ください。
報酬:11,000円/1回
この他に仙台駅からの交通費が発生します。
貸会議室利用の場合はその費用も発生します。
片道2時間以上かかる場合は日当として11,000円追加で頂きます。
こんな法人様にお勧めなサービスです
・従業員の方の平均年齢がお高めの法人様
➡同じ時期に介護離脱希望者が重複する可能性が高いです。
・テレワークが行いにくい業種の法人様
➡仕事と介護の両立方法が限られてしまいます。
・女性従業員の比率が高い法人様
➡令和の現在でも、「介護は女性の仕事」という考えの人は残念ながら存在します。
介護発生前にセミナーを受けておくことで、そのような圧力に応じる必要は無いという自信を持って頂けるかと存じます。
・従業員数が多く、介護トラブル相談数も多く見込まれる法人様
➡介護の押しつけ問題は20~30代の方にも及ぶことがあります。
当事務所では様々な理由での押しつけ対策を揃えています。